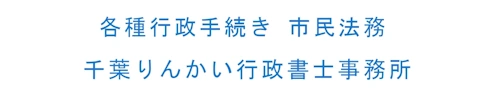古物営業許可の必要性
そもそも古物とは・・・法律上の『古物』
「古物」=「古い物のことじゃないのか」という印象は間違いではありませんが、
「古物営業法」という法律では「古物」を以下のように、少しややこしく定義しています。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
第二条一項 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物営業法 第二条第一項
「使用」の意味
「自動車、バイク→乗る、走らせる」「ギター等の楽器→弾く・叩く」というように、
その物の本来の用途・用法に従って使用するという意味です。
では、「絵画」はどうでしょうか? 絵画の用途は「鑑賞する」ということになります。
本来の目的に従って使用することができない物は「古物」に該当しません。
「使用されない物品で使用のために取引されたもの」について
「自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたもの」とされています。
自分で購入した物も含め、贈答目的で購入された商品券や食器セット等、
小売店等から一度でも消費者の手に渡ったものは、未使用でも法律上「古物」となります。(警察庁通達・解釈基準)
「これらの物品に幾分の手入れをしたもの 」について
「その物の本来の性質、用途を変えず」に、修理、補修等することです。
自転車のパンクを直したり、包丁の錆を落として研ぎ直すなどがわかりやすいです。
「古いカバン」→「加工」→「財布」 といった場合の「財布」は、古物ではなく、
古いカバンを材料として加工して作った「新品」の財布です。
※関係法令等 古物営業法、同法施行令、同法施行規則、警察庁通達(解釈基準)
古物の分類(13品目)
「古物」は以下のように区分されており、13品目の中から「主として扱う品目(ひとつ)」「取り扱う古物の区分(複数)」を選択して申請します。
美術品を選んだ場合には、「許可番号 美術品商 ○○商店」のようになります。
「取り扱う古物の区分」として複数を選択できますが、扱う予定のないものは選ばないほうが賢明です。
| 品目 | 例 |
|---|---|
| 美術品 | 絵画、書道具、彫刻、陶芸品、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀など、「美術品として価値がある」もの |
| 衣類 | 着物、帽子、布団、敷物など |
| 時計宝飾品類 | 時計、眼鏡など、個人的な好みで選んで身に着ける物の他、オルゴールなどもこの品目になります |
| 自動車 | タイヤ、アルミホイール等の部品を含みます。 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | エンジンや各種パーツを含みます。 |
| 自転車類 | ハンドルや椅子、カゴの他、空気入れも含みます。 |
| 写真機類 | カメラ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡など |
| 事務機器類 | パソコン、プリンター、コピー機、シュレッダーなど |
| 機械工具類 | 家電、電動工具、ゲーム機他、スマホやタブレットなども |
| 道具類 | 家具、食器類等の日用雑貨、楽器、ゲームソフト等の光学ディスク、工芸品(美術的価値のない物)おもちゃ類など |
| 皮革・ゴム製品類 | かばんや財布、靴、毛皮類など |
| 書籍 | 雑誌やパンフレット類も |
| 金券類 | 商品券、ビール券、乗車券、航空券、入場券、回数券、切手、印紙、テレホンカード、株主優待券 など |
個別に、法律や条約で取り扱いが規制されている物もあります。
【例】火縄銃、日本刀→銃刀法、象牙、べっ甲→種の保存法、ワシントン条約 その他 家電リサイクル法、消費生活用製品安全法 などなど
法律上、古物とならないもの
古物営業法の目的は、「盗品等、犯罪被害品の流通防止と早期発見、被害の回復」です。その為、
盗難など犯罪被害の可能性が低い物、発見しやすい物は適用されません。
また、本質的な変化を加えなければ使用できない物、消費して無くなる物も「古物」に該当しません。
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量1tを超える機械で、簡単に取外し・運搬ができないもの。
- 重量5tを超える機械で、自走・運搬ができないもの。
- 庭石
- 石灯篭
- 空き缶や金属原材料、古新聞、被覆のない古銅線類など「原材料」となるもの(専ら物)
- 消費して無くなるもの (例)お酒、食品、化粧品など
- その物本来の用途や性質を変化させたもの(例)着物→ハギレなど
- 再利用せずに廃棄するもの(例)一般ゴミなど
- その物の実体がないもの(例)デジタルチケット 、デジタルギフト券など
(目的)
古物営業法 第一章総則 第一条
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物営業とは
上記のように定義された古物を「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」 するのが古物営業です。
古物営業には、1号営業(古物商)、2号営業(古物市場主)、3号(古物競りあっせん業)までありますが、
ここでは需要が多い1号営業についてご説明いたします。
条文はややこしいので、許可の要・不要をケース別に分けます。
許可が必要なケース
- 古物の買取販売
- 古物の買取、修理販売
- 買い取った古物の部品販売
- 手数料の発生する委託販売
- 古物を別の物と交換すること
- 古物を買い取り、レンタル、リースすること
- 国内で買った古物の輸出販売
- ネットオークション等を利用した古物の転売
以上のような場合には、許可が必要となります。
無許可営業には罰則(懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科)が課せられます。
許可が不要なケース
- 自分で使っていた物(不用品)を売ること(※転売目的で無いもの)
- 無償で引き取った古物を販売すること
- 海外で買ってきたものを売ること
- 古物の買取を行わず販売だけを行う
- 自分が販売した物品を、その売却相手から買取ることのみを行うこと
- ネットオークション等を利用した新品の転売
(定義)
古物営業法 第二条第ニ項
第二条第ニ項 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの。
欠格事由
個人の場合は申請者本人と管理者、法人の場合は役員と管理者が、下記の欠格要件にひとつでも該当していると不許可となりますので、事前に必ずご確認下さい。
(1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 犯罪歴
- 禁固以上の刑(罪種問わず)に処せられ、刑の執行終了から5年を経過していない者(執行猶予期間中も含む)
- 古物営業法違反(無許可営業、不正手段による許可取得、名義貸し、営業停止命令違反)で罰金刑を受け、刑の執行終了から5年又は執行猶予満了期間から5年を経過しない者
- 特定の刑法犯(窃盗罪、背任罪、 遺失物等(占有離脱物)横領罪、 盗品等有償譲受け等の罪)で罰金刑を受け、刑の執行終了から5年又は執行猶予満了期間から5年を経過しない者
(3) 暴対法関係
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為をする恐れがあり、過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがある者
- 暴対法規定による中止命令等を受けた者であって、当該中止命令等を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 一般人が暴力団等に威力行使等を依頼し、公安委員会より命令や指示を受けた場合も該当します。
(4) 住居の定まらない者
(5) 古物営業法違反により許可を取消され、5年を経過していない者
(6) 古物営業法違反による許可取消し回避のため、当該処分前に自主返納があった場合、その返納した日から5年を経過していないもの
(7) 心身の故障により適正な古物商業務ができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
(8) 未成年者(18歳未満)※以下の場合には未成年者でも取得が可能です。
- 古物商の相続人で、保護者等の法定代理人が欠格要件に該当しない場合。
- 保護者等の法定代理人から古物商営業の許可を受けている場合。
- いずれの場合も、保護者等による営業許可証明、商法第5条による未成年者登記が必要です。
(9) 「管理者」が、未成年者、欠格要件に該当する場合。
(10) 法人役員に、1~7までの欠格要件に該当する方がいる場合。(監査役含む)
犯罪歴、暴対法関係についてご不明な点はご相談ください。※守秘義務がございますのでご安心ください。
ご依頼の流れ
料金
証紙代金(法定)19,000円
作成中
個人申請
法人申請
変更届等 20,000円~
ー